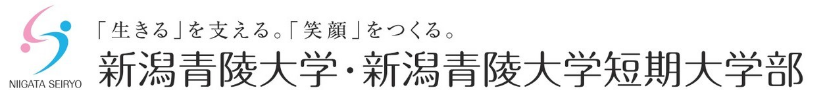子ども発達学科の目的

福祉心理子ども学部の目的
福祉心理子ども学部の教育上の目的は、生命尊重・人間尊重の理念に基づき、人々の生活の質の向上をはかるため、社会福祉学及び心理学の専門知識・技術の応用力、豊かな感性、国際感覚を持ち合わせた専門職業人を養成することにある。(新潟青陵大学学則 第3条第4項)
目標
- 幼児教育・保育に関する高い専門性と実践的能力をもち、自らの経験を体系化して他と共有し続ける人材を養成する。
- 子ども家庭支援に関する高い専門性と実践的能力をもち、自らの経験を体系化して他と共有し続ける人材を養成する。
- 子どもの発達やそれを促す環境と働きかけに関する専門知識をもとに、市民として他者と協働しながら社会の中で役割を果たす人材を養成する。
- キャリアステージに応じて、新たな知見を求め続け、研鑽し続ける人材を養成する。
学科が求める人物像(アドミッション・ポリシー)
- 幅広くものごとに関心を持ち、基礎的な知識を身につけていて、子どもの発達や子どもを育む環境について興味深く学んでいける人
- ものごとを様々な面から捉え、順序立てて考えようとする姿勢を身につけており、子どもの育ちをめぐる課題解決に取り組む方法を意欲的に学んでいける人
- 子どもが持つ可能性や「伸びようとする芽」を大切にする心を持ち、その子らしさを伸ばす関わり方について、積極的に学んでいける人
学びの基本方針(カリキュラム・ポリシー)
- 専門の学びを支える豊かな教養を身に付けるとともに、多様な価値観を理解するための科目を配置する。
- 子どもの発達過程を理解し、最善の発達を促すための環境と働きかけに関する基礎的な知識と倫理を身に付ける科目を配置する。
- 子どもの発達にあわせた教育・保育の内容・方法と、これと密接に関連する子ども家庭支援の方法を学ぶ科目を配置する。
- 子どもの発達を巡る課題を発見・分析し、解決策を見出す力を身に付ける科目を配置する。
- 主体的に学び続けるとともに、多様な人々の価値を認め、協働する態度と力を身に付ける科目を配置する。
- 評価は、学修目標の到達度を厳正に適用し、多様な評価の視点を取り入れることにより、学修成果の適正な評価の充実を図る。
学科がめざす人物像(ディプロマ・ポリシー)
- 子どもの発達やそれを促す環境と働きかけに関する確かな知識・技能を身に付けている。
- 子どもの発達を巡る現代的課題の分析と追究を行うことができる。
- 自らの個性を育みながら、子どもの健全な発達を支えるために多様な人々と力を出し合うことができる。