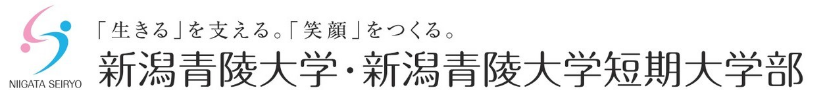シンボルマーク・学園歌

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部
「シンボルマーク・ロゴ」デザイン

応募者製作意図
青陵大学の頭文字「S」をイメージしました。そこに、青陵大学の学問を学ぶだけでなく、学生に対して、人を思いやる「こころ」を根源に育てるという教育方針を表現したく、人と人が互いに向かい合い手を取り合う形をデザインしました。またブルーは校章にも使用されており、更に心(ハート)を表すピンクを使うことで若々しさと、やさしさ思いやりを表現しました。全体をシンプルにすることで、大学の品格を損なわないよう配慮し、小さく使用してもイメージを損なわず判読しやすいデザインにしています。
デザイン
藤田 麻衣(東京都)
「シンボルマーク・ロゴ」の利用について
「シンボルマーク・ロゴ」を利用する場合は、事前に新潟青陵大学に利用の申請をしてください。
学園歌
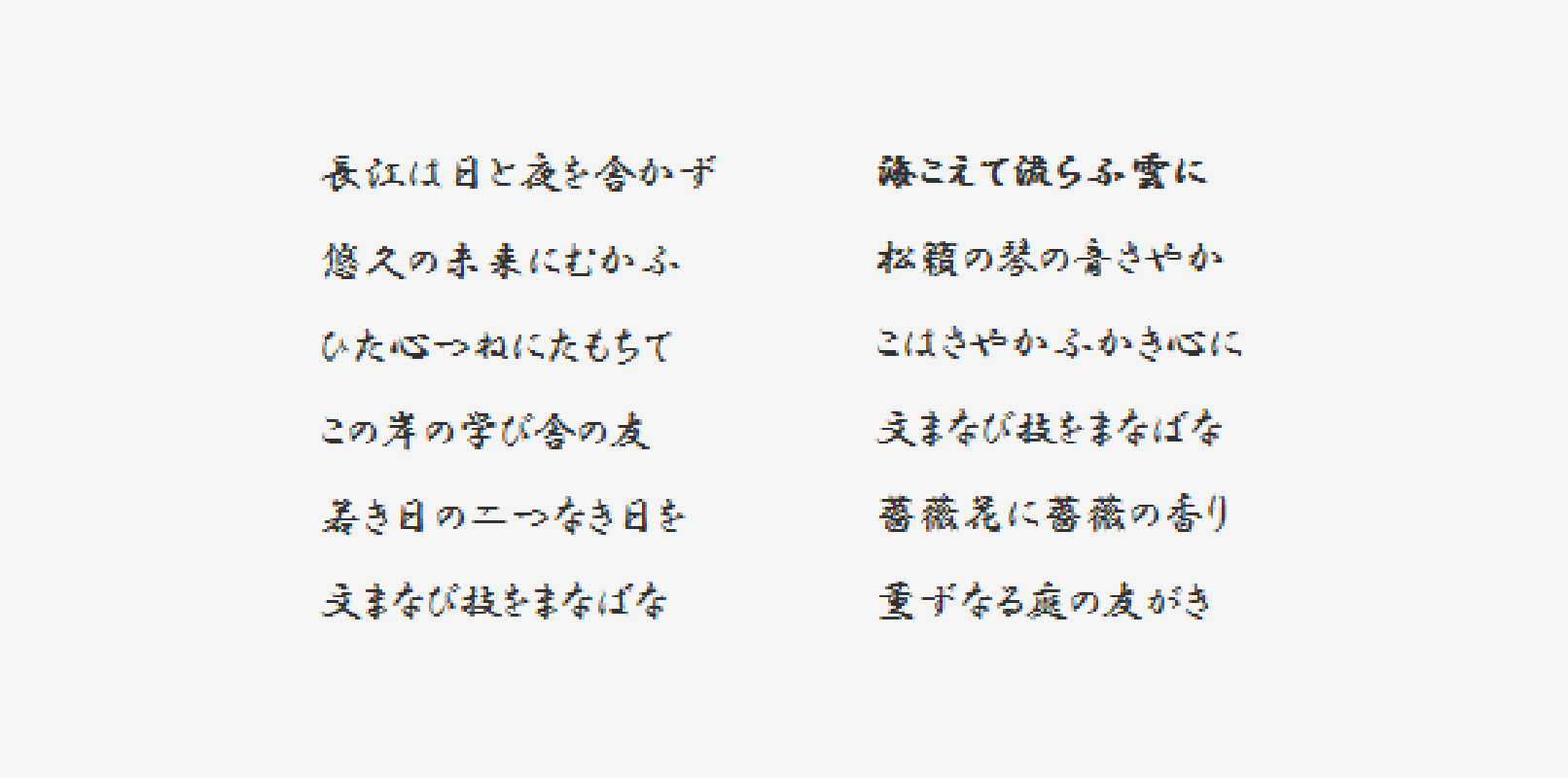
詳説
この詞は、五七調からなり高雅にして調べなだらかにして気品高く唱われております。歌詞の出だしにある「長江は…」長い川のことで、ここでは信濃川のことを指しています。また、「日と夜を舎かず…」は論語の一節から引用したもので、ここでは時間がとめどもなく流れてゆくように、私どもは休みなく理想に向かって努力をしなければならないという意昧であります。
曰、逝者如斯夫。不舎昼夜。
孔子様が川のほとりに(川の上、船に乗って川に出たのではなく)、川の岸におられて、のたまわく、逝く者はかくの如し、この「夫」は「か」と同じ感動を表すことば。『逝く者はかくの如きか、昼夜を舎(お)かず』、歌詞にある「日と夜」は昼夜と同じ意味である。
「悠久の未来にむかふ…」
悠久の未来に向かってということで、先ほど“休みなく理想に向かって努力”と説明したように理想に向かっての意味です。
「ひた心…」
ひた心というのはまっすぐな心を指しております。川は自然現象ですから、いつもひとつの心で流れてゆくということの意味で…、まっすぐな心を常に持って欲しいということであります。
ここまでが学園歌の前置きであります。
「この岸の…」
ここからが学園歌というか校歌の始まりとなります。この学園は、今では信濃川から少し離れておりますが、昔は信濃川の近くの市内の西堀(現在は道路となって西堀通に)のほとりに校舎があったということであります。「学び舎…」、これは学校を指します。
「若き日の二つなき日を…」
これは文字そのもので、人生はニつないから大切にしなければならないという意味であります。
「文まなび技をまなばな…」
学校は学問をされるところですし技術を学ばれるところであることを指しております。
学園歌の第2章は、この学園の地理的な環境をうたっております。
「海こえて流らふ雲に」
雲は目に見えるもので天上のもの。海は地上のもの。これはひとつの対比を表しており、第1章の「日と夜を舎かず」にある昼夜と同じように対比の方法は同じであります。
「松籟の琴の音さやか…」
これは松の間を渡る風の音が琴の音のようにという意味です。琴のように聞こえないかもしれませんが、ここではそれに見立てているということであります。
「こはさやかふかき心に…」
こはさやかは、琴の音が澄んで、はっきりと聞こえることを指しております。なお、参考までに「こは」とは「あら」とか「おや」とかのように驚きのことばです。
「薔薇花に薔薇の香り…」
薔薇の花は目に見えるものです。形や色が…。これを姿とすれば、匂いは目に見えないものです。ここでも二つのものを対比させて詩がつくられている訳です。
「薫ずなる庭の友がき…」
香りがにおう校庭の友垣、友垣は友だちが大勢並んでつながって垣根みたいになるから友垣というのだそうであります。
何気なく口すさんでいた学園歌ですが、今回の解説を機会に歌詞の意味をご承知置きいただきたいと存じております。なお、筆者があらためて申すまでもないことではありますが、作詞者の三好達治先生は、日本の代表的な詩人であります。また、作曲者の中田喜直先生は、「雪の降る町を」「めだかの学校」「小さい秋をみつけた」などの美しい曲で知られる日本の代表的な作曲家であります。