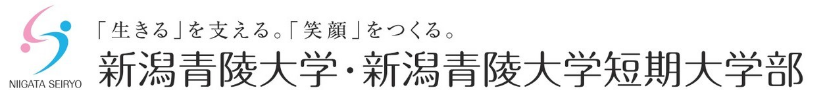教員紹介 - 圓山 里子


助教
圓山 里子Satoko Maruyama
- 担当学科
- 福祉心理子ども学部 社会福祉学科
- 研究テーマ
- 社会福祉学、障害学、障害者福祉、自立生活、地域生活支援、セルフヘルプグループ
- 教員の詳しい情報はこちらへ
- researchmap
Q. 先生の研究・活動を教えてください
私は社会福祉系の学部学科の出身ではありません。学生時代にひょんなことから参加したサークル、それは障害のある子どもや障害者の皆さんと一緒にプログラム活動を楽しむものでしたが、その活動にすっかりはまってしまい、また、社会学の先生から紹介された書籍『生の技法』(初版1990年)もきっかけとして、自立生活運動に興味をもちました。そして、修士論文に取り組む際に、日本で自立生活センターを設立してきた障害当事者に直接教えを受け、その後、いくつかの仕事を手伝ったことが研究活動の原点です。つまり、私の師匠は障害者の皆さんなのです(研究上の師匠・諸先輩は他にいますが)。
こうした経緯から、どのような障害があろうとも、自らが望む地域での暮らしを実現するために必要な仕組みや方法を検討することを研究テーマとしています。
Q. この分野の面白さは、どんなところですか?
「障害」について考えることで、思いもしなかった世界が広がり、様々な「あたりまえ」があることに気づく楽しさがあります。それは、時として自らの内面にある差別性と対面することでもあり、しんどいことです。しかし、だからこそ、この社会のあり方を見直すことができます。
自立生活運動が提唱した自立とは、「人の手助けを借りて15分で衣服を着、仕事に出かける等社会参加できる方が、自分で衣服を着るのに2時間かかるために家にいる他はない状態より自立した生活である」といったものです。最近は、「自立は、依存先を増やすこと」と述べている人もいます。この定義を知った時、びっくりして、そしてほっと楽になった自分がいました。
社会福祉は人と社会の変化にかかわる仕事だと私はとらえています。サポートを得ることで人は変わるし、多くの人たちの尽力によって社会はよりよくなる、それを実感できることが障害分野の面白さです。
授業紹介
障害者福祉論Ⅰ
社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士の国家試験受験資格科目なので、当然、それらの試験に対応できるように様々な法制度や障害者福祉の歴史等を学びます。ソーシャルワークの特色の一つは社会資源を活用した援助ですから、社会資源としての制度施策の基本的理解は必須知識といえます。
しかし、同時に、あるいはそれ以上に重視しているのは、障害の社会モデルの理解です。障害の社会モデルとは、心身機能に制約がある人々にとっての困難=障害は、社会の仕組み(環境や制度や価値観等々)が生み出していると捉える考え方のことで、『障害学にもとづくソーシャルワーク』(1983年、邦訳2010年)で整理された概念です。現在、障害者差別解消法で民間事業者に対しても「合理的配慮」の提供が義務づけられていますが、「合理的配慮」は障害の社会モデルを基盤としています。
障害の社会モデルを基点として障害者福祉を学びます。
メッセージ
コスパタイパがもてはやされる世の中ですが、社会福祉を学ぶ上で無駄な経験はありません。回り道や道草にみえるかもしれないところに面白いことがかくれているかもしれません。まずは存分に高校生活を楽しみ、あるいは楽しめなかったとしても、身近な暮らしの中のちょっとした違和感や疑問をもって大学にきてください。一緒にその疑問を考えていきましょう。
また、新潟青陵大学は海や松林に近いですが、「新潟のまち」にでかけるにも便利なところです。学生時代を大学内外で楽しむにはとてもよい場所ですよ!
著書
- 障害者福祉[第4版](共著)
- パーソナルアシスタンス―障害者権利条約時代の新・支援システムへ(共著)