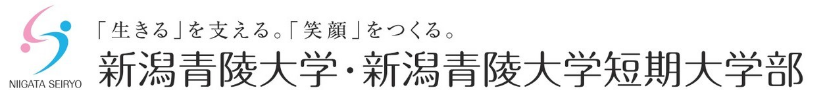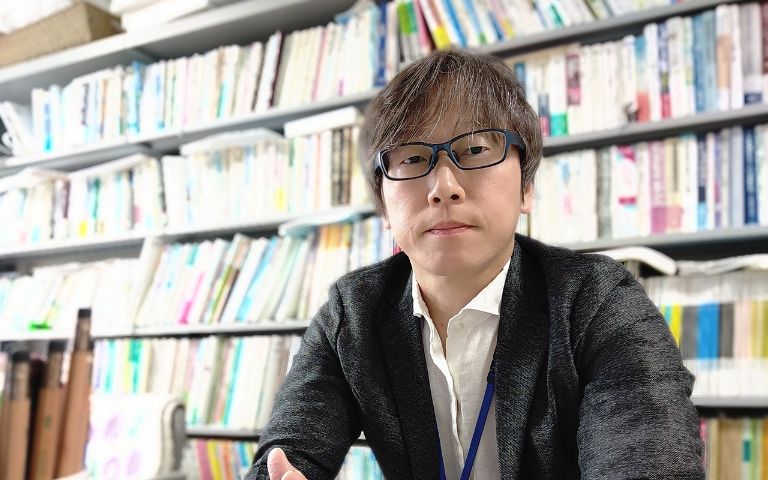教員紹介 - 三浦 修

Q. 先生の研究・活動を教えてください
災害の多いわが国において、災害時の社会福祉とその具体的な援助行動の形態としてのソーシャルワークは、災害医療や災害看護と同様に研究が強化されるべき分野です。また、それを担う人的準備は平常時から促進して取り組むべき課題となっており、そのための教育内容を考えることが私の研究テーマです。 災害時に被災者及び被災地支援に貢献できる人材、被災地から求められる「ソーシャルワーク専門職者としての人材像」を明らかにし、コンピテンシー・モデルを開発するために、被災地のソーシャルワーカーにインタビュー調査をしたり、被災地でコミュニティ形成支援を行うNPOやコミュニティビジネスの活動に実際に参加するなどフィールドワークによる調査を継続して取り組んでいます。
Q. この分野の面白さは、どんなところですか?
災害時の社会福祉を考えるためには、実際に被災された人の状況や思いを聞くことが何よりも大切です。特に災害時には、医療の必要性の高い人や高齢者、障害がある人、子どもなど平常時から支援が必要な人に被害が集中します。これを防ぐためには、平常時から個別の避難計画を作ったり、個別の支援計画を策定して、関係者で共有しておくことが大事です。つまり、災害時の備えをしておくことは平常時のケアの質を高めることにつながっているところ、また、復興まちづくりや防災コミュニティづくりなど地域支援は、誰も住みやすく活気あるコミュニティ、持続可能な地域社会づくりでもあり、将来のわたしたちの暮らしにつながっているところに、この分野の面白さがあると思っています。
授業紹介
社会福祉原論
みなさんは「社会福祉」と聞くと、どんなイメージを持ちますか?
「高齢者の介護」「生活保護」「障害のある人の支援」…きっと、そんな言葉が思い浮かぶ人も多いでしょう。もちろんそれは社会福祉の大事な部分です。でも、実はもっと広くて、もっとワクワクする世界が広がっています。たとえば、「子ども食堂」。地域の人が協力して、子どもが安心してご飯を食べられる居場所を作っています。これも社会福祉。でも同時に、ただの制度ではなく、市民の工夫と行動から生まれたソーシャルイノベーションなんです。つまり社会福祉原論を学ぶことは、「人や制度の歴史」を知ること、「地域で何ができるか」を考えることにつながります。みなさんが、もし「社会を良くする仕事がしたい」と思っているなら、社会福祉原論はぴったりの入口になるはずです。なぜなら、社会福祉原論は、過去を学ぶ授業であると同時に、「新しい未来をデザイン」する授業でもあるからです。
メッセージ
私がこの分野に関心をもったきっかけは、病院で医療ソーシャルワーカーの仕事をしていたときの難病患者さんとのかかわりでした。”生きづらい”と感じている人がとても多くいらっしゃいました。生きづらさをもたらすものは何なのか?医療ソーシャルワーカーとして患者さんとのかかわりの中で考えてきました。そして、分かったことがあります。生きづらさをもたらすものは、その人のなかにではなく、その人を取り巻く環境のなかにあったのです。環境とは、さまざまな関係性のことです。人と人との関係、人と社会との関係、さまざまな関係性に着目していくことが大切なことなんだと患者さんが教えてくださいました。みなさんもまずは自分自身を取り巻く環境、関係性をしっかり見つめてみてください。きっと、ソーシャルワークの醍醐味や奥深さがわかるはずです。
著書
- 精神保健福祉士の仕事
- コミュニティビジネスで拓く地域と福祉
- 医療福祉入門 患者とよい関係を築くために