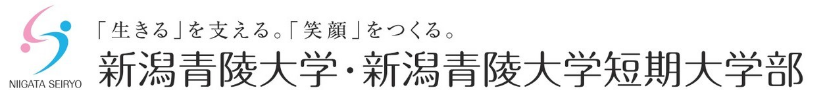Q. 先生の研究・活動を教えてください
私の研究テーマは、長らく携わっている「質の高い社会福祉専門職養成教育とは何か」についてです。近年では自主夜間中学校での講師ボランティアを通して、様々なご事情で学びたくとも学べなかった方々への基礎教育保障について、また、夜間中学では外国人も多く学んでいることから、外国人の日本語習得にも大いに関心を寄せています。在籍している後期博士課程では「外国人介護職員の地域定住」について、「アクターネットワーク理論(ANT)」を用いて研究を進めています。少子高齢社会に伴う日本の介護職員不足は非常に深刻ですが、外国人介護職員を単に労働力の補完とするための地域定住を考えるのではなく、そもそも「定住」には「移動(mobility)」の可能性が前提でなければならないため、固定した関係に落ち着くことではない絶え間ない相互変容(関わりあい)があってはじめて「定住」が成り立つものであり、このプロセスを見るうえで有益な方法がANTだと考えています。
Q. この分野の面白さは、どんなところですか?
ANTの面白さは、人間と非人間の区別なくさまざまなアクター同士のつながり(network)を作り出すことで、社会は常に変化し続けていると考えるところです。マジョリティの中で暮らすマイノリティである外国人介護職員の生きづらさ(生活のしづらさ、仕事のしにくさ)などを、かれらを取り巻く人間と非人間を含めた多種多様な「社会的なもの」をANTを用いて組み直し、従来の制度的支援のみならず新たな支援モデルを開発し提案していきたいと思っています。また、外国人が日本の要介護高齢者を介護する上での諸連関を明らかにすることで専門性をもった介護職員養成へもつながると考えており、私の従来の研究テーマへと発展させていきたいです。加え、日本人、外国人といった二項対立が前提の「共生」を超えた「まあい」をうめる、誰しもが現実の中で生きているという「共に生きる」概念の理解を進めていきたいと考えています。このように、私自身積み重ねた研究が円環的につながりつつあるので、研究すること事体が面白いなと実感しているところです。
授業紹介
ソーシャルワークの基盤と専門職、ソーシャルワークの理論と方法
今現在ソーシャルワークの最終形態は「ジェネラリスト・ソーシャルワーク」にあります。ジェネラリストの視点とは、ソーシャルワーク専門職がどのような価値規範や倫理、知識、技術に基づいて、どのように人や社会に対する認識をもつのかを示すものです。地域共生社会の実現に向けて複合化・複雑化した課題に対応する相談援助を実施し、地域住民などが主体的に地域課題を解決していくよう支援できるソーシャルワーカーをジェネラリストの視点をもちつつ目指します。「ソーシャルワークの基盤と専門職」ではソーシャルワーカーとしてのいしずえを築き、「ソーシャルワークの理論と方法」では具体的な技法を学び実践力を磨いていきます。
メッセージ
私は教員になる前、高齢者施設の生活相談員(社会福祉士)として長らく勤務しました。若手の頃は時に仕事に慢心することもありましたが、地方からきた新人の私に、利用者の皆さん一様に優しく励ましの言葉をかけてくださいました。日々の利用者の皆さんとの受容、共感的理解をもったコミュニケーションの積み重ねにより、「あぁ、こうやって私はソーシャルワーカーとして成長させていただいているのだな」と、ケアする側がいつしかケアされる側にもなっていることを実感した際は大変驚くと同時にとてもあたたかい気持ちになりました。これこそ、私が思う「共に生きる」の原点なのかもしれません。もちろん、ソーシャルワーク専門職として、利用者の皆さんの最善の利益を守るため業務遂行能力は前提にあらねばなりませんが、あたたかい心とさえる頭、両方をもち合わせてこそ福祉のプロフェッショナルといえると思っています。高校生の皆さん、一緒に福祉のプロフェッショナルを目指してみませんか。